隅田八幡神社
隅田八幡神社は和歌山県橋本市隅田町に位置する歴史ある神社で、859年に創建されました。 主祭神は誉田別尊、足仲彦尊、息長足姫尊で、旧県社の社格を持ちます。 毎年10月15日に例祭が行われます。神社には国宝に指定されてい…
 未分類
未分類
隅田八幡神社は和歌山県橋本市隅田町に位置する歴史ある神社で、859年に創建されました。 主祭神は誉田別尊、足仲彦尊、息長足姫尊で、旧県社の社格を持ちます。 毎年10月15日に例祭が行われます。神社には国宝に指定されてい…
 未分類
未分類
奥の院は高野山の信仰の中心地であり、弘法大師空海の御廟がある聖地です。 一の橋から御廟までの約2キロメートルの参道沿いには、約20万基もの墓石、供養塔、慰霊碑があり、「日本の総菩提所」として知られています。 高野山は世…
 未分類
未分類
奥の院墓地は高野山の中でも特に霊気あふれる場所で、弘法大師空海の霊廟へと続く参道にあります。 約2キロメートルにわたる参道には、歴史的な人物や著名な企業の墓など、約20万基の墓石や供養塔が並んでいます。 この墓地は、紀貫…
 未分類
未分類
根本大塔は、日本の和歌山県にある高野山の象徴的な建築物です。 この塔は、真言密教の根本道場のシンボルとして建立され、48.5メートルの高さを誇る日本で最初の多宝塔として知られています。 塔内には、真言密教の教義を体現…
 未分類
未分類
壇上伽藍は、高野山の中心に位置する、歴史的にも宗教的にも非常に重要な場所です。 約1200年前に嵯峨天皇の命により、弘法大師空海が開いた密教の修行場として知られています。高野山で最初に開かれた聖地であり、その精神性の核と…
 未分類
未分類
金剛峯寺は、和歌山県の高野山にある真言宗の総本山。 これは高野山の宗教的な活動の中心であり、多くの重要な寺院や歴史的建造物が集まる場所だからなんですよ。 明治時代初期に発布された神仏分離令によって、かつては高野山全体を指…
 未分類
未分類
日本三景の一つ、天橋立を望む絶景の地に位置し、西国巡礼の第28番札所としても知られています。 このお寺は、身代わり観音の伝説で有名で、願いが叶う(成就する)聖地として親しまれています。 本尊は聖観世音菩薩で、美人観音とし…
 未分類
未分類
浦嶋神社、または宇良神社としても知られるこの神社は、浦嶋太郎伝説の発祥地として有名です。日本最古の正史「日本書紀」に記された浦嶋伝承は、今もこの地で受け継がれています。ここでは玉手箱や重要文化財の掛幅を使った絵解きなど、…
 未分類
未分類
4月中旬から下旬にかけて、朱色の鳥居を背景に山肌が「みつばつつじ」のピンク色の花で覆われる絶景が見られます。 この地域には約1000本のみつばつつじが群生し、毎年鮮やかなピンクの花を咲かせます。 山頂にある展望台からの眺…
 未分類
未分類
元伊勢として知られるこの古社は、伊勢神宮に奉られる天照大神と豊受大神がかつてこの地から伊勢へ移されたという伝承に由来します。 奈良時代には丹後国の一の宮として、また平安時代の「延喜式」では名神大社として認定され、山陰道で…
 未分類
未分類
元伊勢籠神社の奥宮、久志濱宮(くしはまのみや)としても知られるこの神社は、「くし」という神秘的な力の源泉として、現在多くの人々にパワースポットとして親しまれています。 本殿の裏手には、約2500年前から変わらぬ姿で守られ…
 未分類
未分類
天橋立に静かにたたずむこの神社は、恋愛成就のパワースポットとして知られています。天橋立に伝わる数々の龍伝説の中で、ここでは特に八大龍王が祀られています。神社のすぐ隣には、日本名水百選に選ばれた「磯清水」があります。海に囲…
 未分類
未分類
関西花の寺3番礼所。平安時代初頭に高丘親王によって開かれ白河天皇が中興したと伝えられる金剛院。 三重の塔、本堂、雲山閣などが周囲の景観と溶けあって、訪れる人たちの心を引きつける。 春の新緑や冬の雪景色はもちろん、もえるよ…
 未分類
未分類
若狭富士として知られる青葉山の中腹に位置する松尾寺は、西国三十三所巡りの第二十九番札所です。この寺院は、国宝である普賢延命像(絵画)や快慶作の阿弥陀如来坐像など、多くの貴重な文化財を所蔵しています。これらの文化財は、春と…
 未分類
未分類
「鬼嶽稲荷神社」は、京都府福知山市大江町に位置し、丹後天橋立大江山国定公園内の日本百選「森林浴の森」にある大江山の8合目、標高650mに鎮座しています。 この神社は、ブナやナラの原生林に囲まれた自然豊かな場所にあり、鬼(…
 未分類
未分類
本尊・千手観音の霊力で眼病が治ったお礼にと、七色に変化する光の花あじさいを植樹されたのが「あじさい寺」のはじまり。 その後、植えられたアジサイがよく育っていたこと、アジサイが觀音寺の土地に一番合うことから多種植樹され、現…
 未分類
未分類
「一宮神社」は、社伝によれば奈良時代に創建されたと伝えられている歴史ある神社です。 境内には鎌倉時代の石灯籠が残されており、その長い歴史を物語っています。 また、江戸時代には福知山藩の鎮守として栄え、地域の守護神として重…
 未分類
未分類
安国寺は、14世紀半ば、室町幕府の初代将軍、足利尊氏により創建された由緒ある寺院です。この寺院は尊氏が出生した地ともいわれており、境内には産湯の井戸や尊氏とその母・上杉清子の墓も残されています。 本堂には尊釈迦三尊坐像な…
 未分類
未分類
『御霊神社』は、福知山の領主であり善政を敷いた戦国時代の武将、明智光秀を祀る神社です。 光秀は城下町の建設や由良川の氾濫防止のための堤防建設など、町の発展に大きく貢献しました。 逆臣としての汚名を被ったにもかかわらず、市…
 未分類
未分類
「長安寺」は、臨済宗南禅寺派に属し、西国薬師霊場第26番札所、丹波古刹十五ヶ寺霊場の13番札所です。 この寺院は、丹波大文字(姫髪山)の山腹に位置し、境内には重森官完途作による「薬師三尊四十九燈の庭」があり、四季折々の景…
 未分類
未分類
「光明寺仁王門」は、聖徳太子によって599年に創建されたと伝わる光明寺にあります。この寺は、宝治2年(1248年)に建立されたとされ、三間一戸、入母屋造の構造を持つ二重門で、全国的に珍しい栩葺の屋根を有しています。昭和2…
 未分類
未分類
「元伊勢内宮 皇大神社」は、三重県の伊勢神宮が現在地に鎮座する以前に天照大神の神鏡が祀られたと伝えられる、格式高い神社です。 この神社は、第10代崇神天皇の時代に大和地方から移され、その後全国を転々とした後、54年後に伊…
 未分類
未分類
「天岩戸神社」は、天照大神が降臨したと伝わるご神体山岩戸山の麓に鎮座し、櫛石窓戸命と豊石窓戸命を祭神とする神社です。この神社は、幽玄な岩戸渓谷に位置し、神々が天下った地として知られています。参拝者は鎖を伝い、斜面を登って…
 未分類
未分類
京都の京丹波町に位置する玉雲寺は、丹波地方を代表する曹洞宗の禅寺で、その歴史と自然の美しさで知られています。応永23年(1416年)に市森城主・須知氏によって創建されたこの古刹は、京丹波町指定の文化財としても認められてい…
 未分類
未分類
鴻ノ巣山の麓に位置するこの神社は、松の古木が茂る美しい参道を抜けると、本殿、拝殿、社務所が見えてきます。南向きの本殿は、文安5年(1448年)に建てられたもので、檜皮葺きの屋根と正面の千鳥破風が特徴的な、変わり種の建築で…
 未分類
未分類
城陽市にある久世神社は、かつての久世村の産土神として崇拝されていました。この神社は、若王社や白鳥の宮とも称されていたことがあります。創祀された具体的な年代は不明ですが、祭神として日本武尊を祀っています。重要文化財に指定さ…
 未分類
未分類
玉津岡神社の南隣、井手の里を一望できる高台に建っています。 絢らんな様を誇る「しだれ桜」は京都府の天然記念物に指定されており、京都・円山公園の「しだれ桜」の兄弟木にあたります。 京都府綴喜郡井手町井手東垣内16 JR奈良…
 未分類
未分類
笠置寺は奈良時代に創建され、その歴史は東大寺のお水取りの起源とも言われるほど古い。 伝承によると、笠置山で鹿狩りを楽しんでいた天武天皇の皇子が、進退窮まった状況で巨岩の上に立ち、仏に祈りを捧げて難を逃れたとされます。 そ…
 未分類
未分類
京都縁結びパワースポット「恋志谷神社」後醍醐天皇の寵妃を祀る、木津川のほとりにある恋志谷(こいしだに)神社。昔から子授け、安産、婦人病平癒など女性の守り神として信仰されています。 毎年4月と9月の祭京都にある縁結びのパワ…
 未分類
未分類
海住山寺は、京都府木津川市加茂町にある真言宗智山派の寺院で、恭仁京があった瓶原を見下ろす三上山の中腹に位置します。山号を補陀洛山と称し、本尊は十一面観音です。奈良時代に創建され、鎌倉時代に貞慶によって中興された歴史を持ち…
 未分類
未分類
岩船寺は、京都府木津川市加茂町岩船に位置する真言律宗の寺院で、山号は高雄山、本尊は阿弥陀如来です。 開山は行基と伝えられており、アジサイの名所としても知られています。 加茂町南部、かつて「小田原」と呼ばれた南当尾一帯は、…
 未分類
未分類
浄瑠璃寺は、京都府木津川市加茂町西小札場に位置する真言律宗の寺院です。 山号は小田原山で、本尊には阿弥陀如来と薬師如来が祀られており、開基は義明上人によるものです。 寺名は、薬師如来が住むとされる東方の浄土、「東方浄瑠璃…
 未分類
未分類
観音寺は、京都府京田辺市に位置する真言宗智山派の寺院で、山号は息長山です。 本尊は十一面観音で、別名として普賢寺、大御堂、大御堂観音寺などがあります。この寺院は、天武天皇の勅願により義淵僧正によって創建されました。 歴史…
 未分類
未分類
旧綴喜郡にある、日本で最も古い神社の一つとされるこの神社の創建年は明らかではありませんが、平安時代初期に編纂された日本全国の神社を記した「延喜式」に名を連ねており、その時代から朝廷によって崇敬されていたことがわかります。…
 未分類
未分類
酬恩庵は、室町時代に活躍した臨済宗大徳寺派の禅僧、一休禅師によって再興され、彼の晩年を過ごした場所として知られています。 この寺院は、京都府京田辺市に位置し、山号は霊瑞山、本尊は釈迦如来です。一休寺、または「薪の一休寺」…
 未分類
未分類
棚倉孫神社は、京都府京田辺市田辺棚倉に鎮座する神社で、御祭神として大永6年(1526年)の棚倉孫神社紀に記された高倉下命(たかくらじのみこと)を勧請したとされます。この勧請は、推古天皇31年(623年)9月に相楽郡の棚倉…
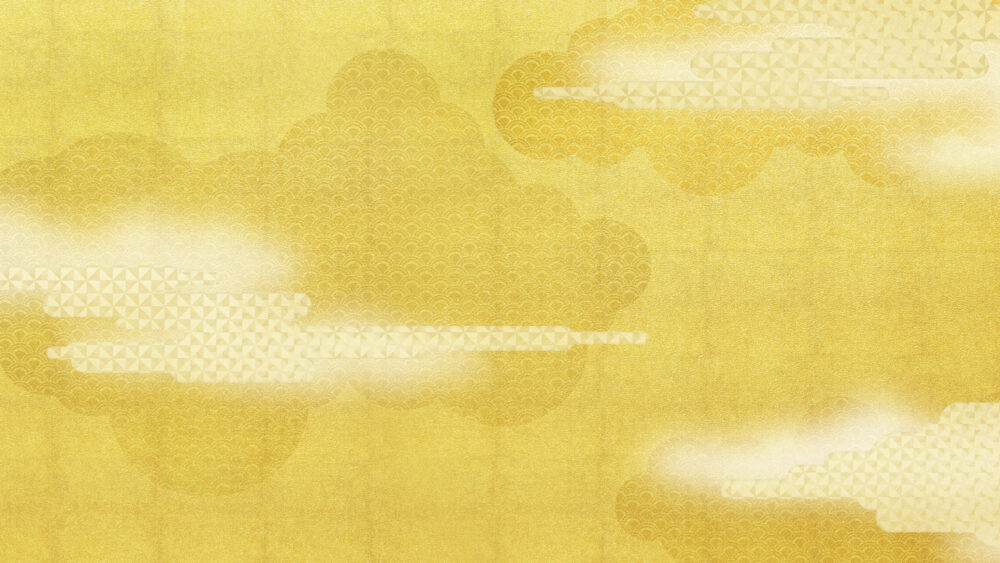 未分類
未分類
白山神社は、市内で最も古い神社建築物として知られ、本殿は重要文化財に指定されています。 この神社は、毎月第1日曜日に朔日講の神楽を行うことで有名ですが、令和3年(2021年)現在は休止しています。 本殿は永享年間(142…
 未分類
未分類
西光寺は、奈良時代の天平勝宝8年(756年)に創建されたと伝えられています。かつては、高雄にある神護寺の末寺として栄え、長い歴史を持つ寺院です。この寺院は、毎年8月16日に奉納される六斎念仏踊りで知られており、この踊りは…
 未分類
未分類
摩気神社は、その創始が古く、延喜式に名神大社として列されています。承暦3年(1079年)には白河天皇の行幸があり、「船井第一摩気神社」の勅額を賜りました。 江戸時代には、園部藩主小出氏の祈願所としても利用された歴史を持ち…
 未分類
未分類
京都の山間に位置する静かなお寺、龍穏寺は、園部市中心部から園部川沿いに約5km遡った農村地帯にあります。普段は訪れる人も少なく静かなこのお寺ですが、紅葉のシーズンにはその美しさが京都はもちろん、全国から多くのカメラマンを…
 未分類
未分類
西国観音霊場十番札所で、本山修験宗の別格本山です。 あじさい寺として有名です。 三室戸寺(みむろとじ)は、京都府宇治市にある本山修験宗の別格本山の寺院。 山号は明星山。本尊は千手観世音菩薩。 西国三十三所第10番札所。初…
 未分類
未分類
南禅寺は、京都市左京区南禅寺福地町にある臨済宗南禅寺派の大本山の寺院。山号は瑞龍山、正式には太平興国南禅禅寺と号する。開山は無関普門。開基は亀山法皇。日本最初の勅願禅寺であり、京都五山および鎌倉五山の上に置かれる別格扱い…
 未分類
未分類
京都を代表する紅葉の名所~もみじの永観堂 禅林寺は、京都市左京区永観堂町に位置する浄土宗西山禅林寺派の総本山です。京都を代表する紅葉の名所で、自らも「もみじの永観堂」と謳っています。 紅葉のハイシーズンには、境内が一方通…
 未分類
未分類
桓武天皇が主祭神の縁結びパワースポット 平安神宮は、明治28年に平安遷都1100年を記念して創建されました。 この神社では、遷都のおや神様である第50代桓武天皇を主祭神として祀り、また孝明天皇も共に祀られています。平安神…
 未分類
未分類
豊臣秀吉を祀る神社 豊臣秀吉を祀る豊国神社は、もともと阿弥陀ヶ峯の中腹に位置していましたが、豊臣家滅亡後に徳川幕府によって破却されました。 その後、明治13年(1880)に明治政府が秀吉の徳を称え、方広寺大仏殿跡に再興さ…
 未分類
未分類
智積院は、真言宗智山派三千ヵ寺の総菩提所・総祈願所。 歴史に彩られた境内や、桃山時代を代表する障壁画で知られる長谷川等伯とその弟子たちによる作品。 そして利休好みの庭として名高い大書院の東側にある庭園は、東山でも随一の美…
 未分類
未分類
全長約120mの本堂をもち、堂の内陣柱間が33あるところから呼び名がついた。正式名称は蓮華王院。「日は永し、三十三間堂長し」と、あの夏目漱石も感嘆の声を挙げた本堂の中には1001体の千手観音立像と28体の護法神像、風神・…
 未分類
未分類
ご鎮座は和銅4年2月初午の日とされ、全国各地に祀られている稲荷神社の総本宮。 同社は古来「衣食住の大祖にして、万民農楽の神霊なり」と篤く信仰されており、中世から近世にかけては商売繁盛・家内安全の神としてご神徳も広く伝播さ…
 未分類
未分類
皇室とのつながりがあるお寺 泉涌寺は真言宗泉涌寺派の総本山であり、皇室との繋がりが深く、御寺としても知られています。「御寺(みてら)」と称され皇室とも繋がりの有るお寺なんです。 伝承によれば、空海が天長年間にここに草庵を…
 未分類
未分類
大石内蔵助らを祀る岩屋寺~通称大石寺 京都には岩屋寺の他にも大石内蔵助を祀る神社がありますが、こちらは大石内蔵助にゆかりのあるお寺。 岩屋寺は、赤穂事件で有名な大石内蔵助良雄にゆかりのある寺院です。岩屋寺は、その本尊であ…