歴史的建造物
ケイズハウス宿泊予約 キネマ通りからちょっと歩くとガラッと雰囲気が変わるエリアがあります。 歴史のある重厚な建物が大川沿いに建っていて風情がある… 平成9年まで旅館業を営んでいた「東海館」2001年に伊東市へ寄贈された後…
 中部の温泉・秘湯ブログ
中部の温泉・秘湯ブログ
ケイズハウス宿泊予約 キネマ通りからちょっと歩くとガラッと雰囲気が変わるエリアがあります。 歴史のある重厚な建物が大川沿いに建っていて風情がある… 平成9年まで旅館業を営んでいた「東海館」2001年に伊東市へ寄贈された後…
 未分類
未分類
世界遺産としても有名な白川郷。世界遺産に登録されている「合掌造り集落」、霊峰白山の麓が源泉地となる「平瀬温泉」、自然豊かな大白川園地の「白水の滝」「白水湖」、「白山ブナの森キャンプ場」(旧大白川野営場)など、伝統の知恵と…
 未分類
未分類
旅した日:2021年7月 あわら市の観光スポット*一乗谷朝倉氏遺跡に行ってきました。 一乗谷朝倉氏遺跡 一乗谷朝倉氏遺跡は、今から約530年前の文明3年(1471)、戦国大名・朝倉氏が5代103年間にわたって越前の国を支…
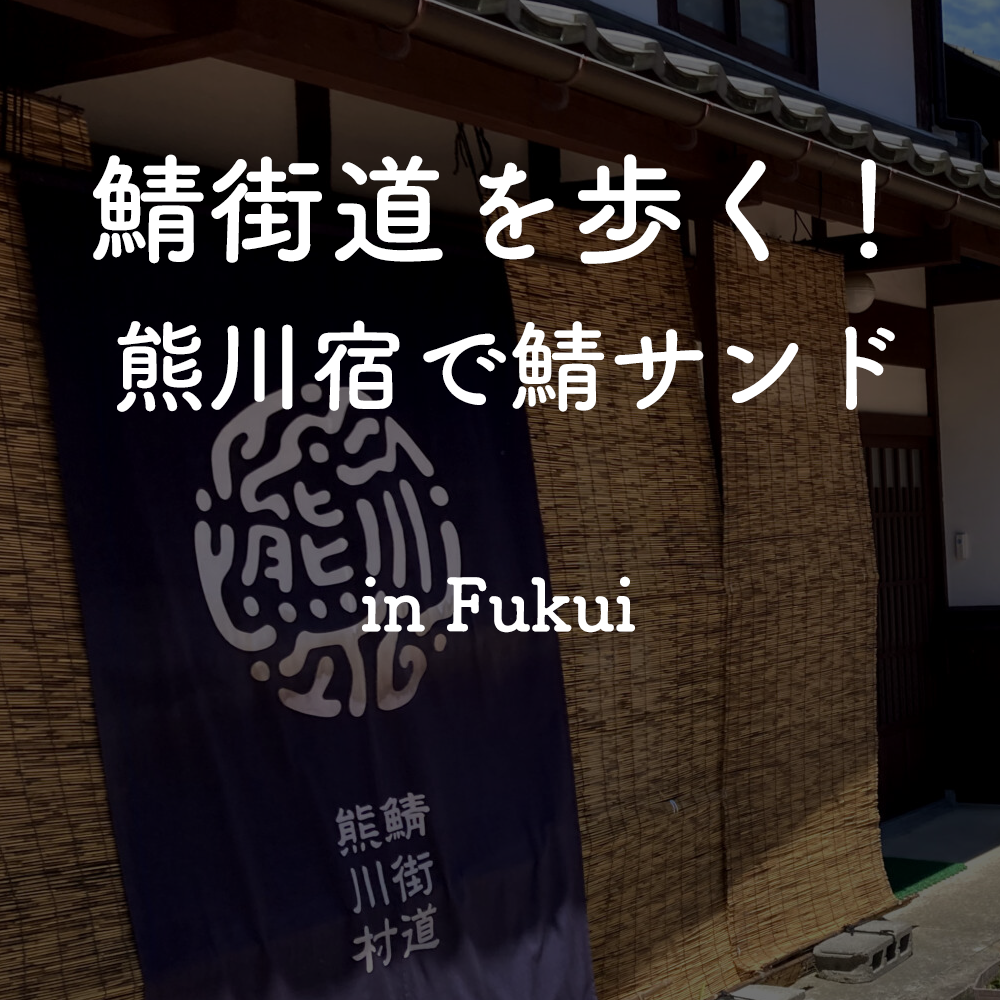 未分類
未分類
鯖街道を歩く!熊川宿で鯖サンド(ツーリング・ドライブが最高)【福井旅行記】 旅した日:2021年7月 出張とオリンピックの4連休を利用して北陸~東海の旅に来ています(現在旅の真っ最中です。旅先でブログなう) 鯖街道って?…
 未分類
未分類
珍しいなまこ壁仕上げの建物 真岡もめん問屋岡部呉服店の2代目岡部久四郎氏が、明治初期に建築材料などを多年にわたって集め、大工・指物師は出入りの職人を修行させて10年余の歳月を費やした建築です。 木造2階建ての土蔵造りで、…
 未分類
未分類
明治の香りを感じる邸宅 道の駅「明治の森・黒磯」の敷地内には、明治時代にドイツ公使や外務大臣を務めた青木周蔵の別邸が建っています。 この洋館は、ヨーロッパ式の建築技術を用いて建てられました。青木邸の前には四季折々の花が美…
 未分類
未分類
平家の落人集落 平家の落人により集落が築かれたといわれ、平家落人の伝説が残る湯西川温泉。平家落人の生活様式を後世に残すため、村内の茅葺き屋根の民家を移築し再現した民族村です。 平家が源平の戦に敗れてからちょうど800年目…
 未分類
未分類
日本の煉瓦建築を支えたホフマン式 野木町煉瓦窯は、赤煉瓦焼成用の「ホフマン式」と呼ばれる連続焼成窯で、明治の近代化に伴い日本の煉瓦建築を支えました。国内には4基のホフマン窯が残っていますが、唯一原型をとどめて保存されてい…
 未分類
未分類
両袖切妻造と呼ばれる貴重な建物 横山家は店舗の右半分で麻問屋、左半分で銀行を営んでいた明治の豪商でした。 両袖切妻造(りょうそできりづまづくり)と呼ばれる貴重な建物には、当時を偲ばせる帳場などが再現されています。 店舗の…
 未分類
未分類
日本国中最も大にして、最も有名な坂東の大学 足利学校は、日本で最も古い学校として知られ、その遺跡は大正10年に国の史跡に指定されています。 足利学校は、応仁の乱以後、引き続く戦乱の中、学問の灯を絶やすことなくともし続け、…
 未分類
未分類
親鸞聖人ゆかりの地 親鸞聖人ゆかりの地「三谷の草庵」 高田山専修寺から東へ約2km行った山のふところに抱かれた小庵。専修寺を建立中、聖人はここを仮住居として利用されていたところと伝えられています。 栃木県真岡市三谷
 未分類
未分類
明治時代後期から大正時代にかけてアメリカで活躍した、河井村(茂木町河井)出身の日本画家・古田土雅堂が帰国の際に輸入した組立住宅。 栃木県芳賀郡茂木町茂木1123
 未分類
未分類
アントニン・レーモンドの建築を楽しむ イタリア大使館別荘記念公園は、栃木県日光市にある公園です。1928年から1997年までイタリア大使館別荘として使用され、建物を修築、復元した上で公園として整備し一般公開しています。 …
 未分類
未分類
明治時代の豪商の姿を今日に伝える 旧篠原家住宅は宇都宮を代表する旧家の篠原家の住宅です。江戸時代(19世紀初めごろ)から奥州街道口の現在の場所で、しょうゆ醸造業や肥料商を営んでいました。 現在の建物は、明治28年に建てら…
 未分類
未分類
現存最大級のロマネスク・リヴァイヴァル建築 カトリック松が峰教会は、栃木県宇都宮市にあるキリスト教の教会およびその聖堂です。 大谷石建築としては現存最大級のロマネスク・リヴァイヴァル建築であり、1998年に国の登録有形文…
 未分類
未分類
飯坂温泉の観光交流拠点 旧堀切邸は、江戸時代から続いていた豪農・豪商の旧家を補修、復元、一部新築により整備し、飯坂温泉の観光交流拠点として平成22年5月に開館しました。 敷地面積は約1,230坪あり、明治13年以前には現…
 未分類
未分類
約300年前の南会津地方の本百姓の家屋 桁行8間半、梁間3間半、床面積117.19平方メートル。 長方形の平面形態の、江戸時代中期、会津平坦部の中堅層農家の家構えであり、梁束に享保14年の墨書が発見されました。 土台がな…
 未分類
未分類
喜多方一の贅沢さを誇る住宅 大正後期 種類:座敷蔵・店蔵 喜多方では珍しい黒漆喰、51畳の座敷蔵、螺旋階段などの喜多方一の贅沢さを誇る住宅です。 座敷蔵、店蔵、醤油蔵が国登録有形文化財に指定されています。 福島県喜多方市…
 未分類
未分類
会津藩の本陣跡 旧滝沢本陣は、福島県会津若松市にある会津藩の本陣跡です。 国の史跡に指定されていて現存する建物のうち、主屋および座敷は、旧滝沢本陣横山家住宅として国の重要文化財に指定、敷地と建物は国の史跡に指定されていま…
 未分類
未分類
定期的にお茶会も開かれる 鶴ヶ城公園内にある、千利休の子・少庵が建てたと言われる茶室です。 お客様がお茶を楽しめたり、定期的に茶会が開かれたりしております。 戊辰戦争後、城下に移築され保存されていましたが、平成2年に元の…
 未分類
未分類
霞城公園内にあり、長年市民に利用されてきた県立病院(のちに市立病院)済生館本館の建物を移築・復元し、あわせて館内に郷土資料・医学資料を展示したものです。 済生館は1878年(明治11年)に建てられた、4階3層の擬洋風建築…
 未分類
未分類
文翔館は、山形県山形市の中心部にある国の重要文化財「山形県旧県庁舎及び県会議事堂」を修復・利活用している施設です。 正式名称は「山形県郷土館」。日没から21:30までライトアップが行われています。 山形県郷土館は、191…
 未分類
未分類
国の登録有形文化財です。 高畠石造りの貴重な建築物で、昭和9年に木造駅舎から建て替えられました。 展示している駅舎のホームと電気機関車から、昭和の面影が感じられます。 山形県高畠町桜木町 高畠駅より車10分
 未分類
未分類
上杉記念館は、1896年に米沢城二の丸跡に上杉家14代茂憲伯爵邸の本宅として建てられました。 しかし、1919年の米沢大火で焼失。 その後の1925年、総ヒノキの入母屋造りの建物として、落ち着いた中に気品がただよう純日本…
 未分類
未分類
旧有路家住宅は江戸初期を下らない時代の創建と見られている建物です。 この住宅は、松尾芭蕉が「おくのほそ道」に記した、堺田のいわゆる”封人の家”と見なされています。 元禄2年(1689)5月芭蕉は2…
 未分類
未分類
湯浅町は、熊野三山へと続く熊野古道の宿場町として栄え、熊野古道が唯一商店街を通る町としても知られています。紀州湯浅は「醤油発祥の地」と知られています。 白壁の土蔵、格子戸や虫籠窓など、醤油醸造の伝統を感じる家並みが残る東…
 未分類
未分類
漆器四大産地のひとつとして400年以上の歴史を誇る紀州漆器の里「黒江」。 京風で趣のある連子格子の町屋が、通りに面して「のこぎりの歯」のように規則正しく並び、歴史を感じる独特な漆器町の景観が形成されてきました。 和歌山県…
 未分類
未分類
旧中筋家住宅は、江戸時代後期の和佐組大庄屋の屋敷として建てられた、歴史的な建物です。この建物は、熊野古道に面した敷地の東側に位置しており、嘉永5年(1852年)に建築された主屋が特徴的です。主屋には、三階建ての望山楼や二…
 未分類
未分類
観海閣は、頼宣が慶安年間(1648年~1652年)に木造の水上桜閣として建立したもので、対岸の紀三井寺と対面しています。(当時の建造物は昭和36年に第二室戸台風で流出。現在はコンクリートで再建されたもの。) 和歌山市和歌…
 未分類
未分類
京都府与謝郡伊根町の伊根地区に位置する伊根の舟屋は、伊根湾沿いに並ぶ独特の民家で、船の保管庫の上に住居が建てられた伝統的な建造物です。この集落は重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、国内外から年間約30万人の観光客…
 未分類
未分類
鉄骨れんが造りでは日本最古級とされ重要文化財に指定。メソポタミアをはじめとする古代文明の遺跡や万里の長城など世界の有名建築物のれんがのほか、日本のれんが建築物なども紹介。 赤れんが博物館は、明治36年に建設された旧舞鶴海…
 未分類
未分類
江戸時代初期に、松倉重政により、五條藩の城下町として開かれました。 松倉重政が肥前・島原藩に移ったため、五條藩は廃止されたが、その後は、大和南部の天領支配の中心地として五條代官所が置かれ、繁栄をつづけました。 五條の歴史…
 未分類
未分類
富山県五箇山地方。 険しい山岳地帯だったゆえに秘境とも呼ばれ、伝統的な合掌造りをはじめ、いにしえの景観や文化が今でも大切に守られています。 移築された合掌造りが13棟あり、五箇山での伝統的な生活を実際に体感できるほか、周…
 未分類
未分類
高岡市伏木気象資料館(旧伏木測候所)は、明治16年に藤井能三らの手によって、わが国初の私立測候所として伏木燈明台の一室に設立されました。 その後二度の移転を経て、平成18年3月には、明治期から残る気象観測施設として高い評…
 未分類
未分類
高岡でも屈指の商家旧室崎家。どっしりとした外観ながら内部は明るく、贅を凝らした土蔵づくりの家の特徴をよく伝えています。 室崎家は、明治初年にこの地に移り住み、1945年まで綿布の卸売業を手広く営んでいました。 現在は、石…
 未分類
未分類
北前船の歴史を残す国指定重要文化財 岩瀬の大町通りにある森家(国指定重要文化財)は、日本海で活躍した北前船の廻船問屋。 館長の名調子とともに楽しく見学することができます。 行きも帰りも荷を載せて「倍倍」に儲かることから、…
 未分類
未分類
北アルプスを背景にひろがる黒部川扇状地。 その田園風景の中に、下山芸術の森があります。 その施設の中心にあるのが、大正15年に建設されたレンガ造りの発電所美術館。 取り壊される予定だった水力発電所を美術館として再生したユ…
 未分類
未分類
柳田村の黒川が天領だった頃の庄屋。4000坪の屋敷からは当時の権力がうかがえます。 圧巻なのは天井・床・壁・階段にいたるまで輪島塗を施した塗蔵で一見の価値あり。 宗和流の庭園も見事で県の名勝に指定されています。 石川県鳳…
 未分類
未分類
加賀藩十村役 喜多家 十の村を単位にした組織の長が十村役です。 加賀藩の前田利常が定めた農政制度で十村役は年貢の取り立てなどをしました。 喜多家は十村役の筆頭で茅葺きの十村役門はその象徴とも言える存在です。 屋敷には藩主…
 未分類
未分類
能登に残る古い型式の農家で入母屋造りの単層茅葺き。 柱はカンナを使った跡がないという単純素朴なもの。 国指定重要文化財。合掌茅葺入母屋造りの口能登型民家。 江戸時代・享保(1716~1735)の建築と推定され、現存する最…
 未分類
未分類
加賀藩家老であった横山家が金沢市の邸内に建てた書院を移築したものです。 明治末期の木造技術の枠を傾けた最高級の普請であったと伝えられています。 成巽閣(重文・金沢)に見られる武家邸宅書院の伝統を継承する近代の書院造として…
 未分類
未分類
大正4年10月、北大路魯山人(当時は福田大観)は金沢の文人・細野燕台の紹介で老舗旅館 吉野屋、九谷焼 須田菁華の刻字看板を彫るため山代温泉を訪れ、吉野屋の別荘を仕事場として数か月滞在しました。 その間、菁華窯で初めて作陶…
 未分類
未分類
マンガロードの道中、十字の交差点に佇む「旧観慶丸(きゅうかんけいまる)商店」。 漁業の盛んな港町のイメージに結びつかない西洋風の外観が、街中でもひと際目立ちます。 もともとは昭和5年(1930)に開業した、石巻で最初の百…
 未分類
未分類
「海商の館 旧亀井邸」は、東北を代表する商社であるカメイ株式会社の初代社長・亀井文平(かめい ぶんぺい)氏が、大正13年(1924)に建てた邸宅です。 伝統的な和風建築に西洋建築を取り入れた「和洋併置式」の邸宅で、この建…
 未分類
未分類
文久3年に加賀藩13代藩主・前田斉泰が母・真龍院の隠居所として建てた歴史的建造物。 歴史博物館として一般公開されています。 兼六園に隣接しているので、兼六園とあわせて寄っておきたい場所です。 群青の間・書見の間 格式のあ…
 未分類
未分類
江戸時代の加賀百万石の名残を今に伝える歴史的建造物が公開されています。 農家ゾーン、町家・武家ゾーンの2つに分かれ、当時の暮らしぶりや生活様式を分かりやすく解説しています。 園内の建物はすべて国指定重要文化財、または石川…
 未分類
未分類
安土桃山時代に、豊臣秀長の家臣によって、宇陀松山城の城下町として整備・拡充されました。 その際、建物の間口の広さによって課される税を免除して、有力な商人を誘致したため、「間口も奥行きも広い」というこの地区ならではの町家が…
 未分類
未分類
西組散策マップ 小浜は昔から京都と深いつながりを有してきました。若狭湾に面する小浜には、今も生活のいたるところに京文化の面影が残っています。 三丁町と呼ばれるかつての茶屋町には、狭い路地、ベンガラ格子や出格子の家が軒を連…
 未分類
未分類
敦賀港の東側に2棟並んで建っている『赤レンガ倉庫』は、福井県内でも有数のレンガ建築物です。 2009年1月には、北棟・南棟・煉瓦塀が国の登録有形文化財に登録されました。 外国人技師の設計によって1905年に建てられた当時…
 未分類
未分類
隣家からの火事を防ぐ卯建(うだつ)があがりひときわ異彩を放つ京藤家は、今庄宿では脇本陣格の建物であり、幕末の国学者・歌人の橘曙覧などの書が所蔵されています。 また、水戸天狗党の一行が宿泊し、刀傷をつけた柱が残っているんで…